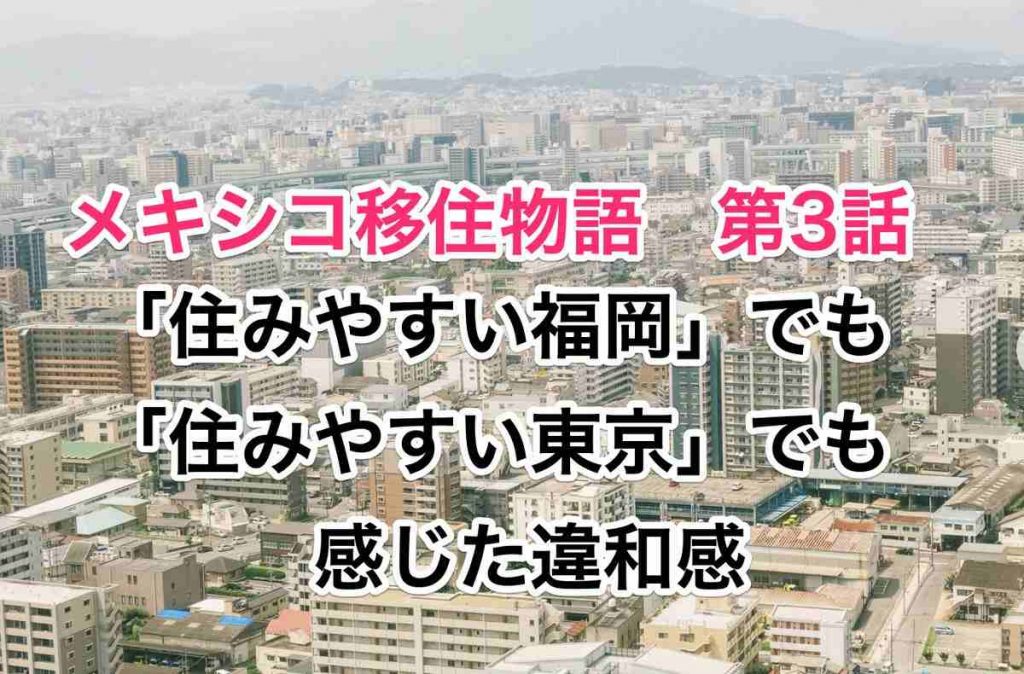~10代までの面倒くさい私と、日本の良さについて~
こんにちは。メキシコ在住フリーランスのワカです。連載第3回。前回は私の抱えていた仕事での葛藤について触れましたが、今回は私が長年感じていた“生き辛さ”について。(これまでの記事はコチラから。)
私は小学生くらいから、事あるごとに「なんで?ちゃんと説明して?」と思うことや「なんで全員一緒じゃないといけないわけ?」と感じることが多々ありました。家庭でも、怒られるときに「ダメなものはダメ!」「子どもだからダメ!」と言われることが日常。生き辛さの本題に移る前に、私のモヤモヤの始まりである懐かしい過去を少しだけ振り返ります。
校則関係&学校日常編(ごく普通の公立小・中・高)
- 整髪料&髪染め禁止
- ブルマ(下着と同じ形じゃん!) ※後に廃止となりました。
- 靴下・靴の指定(ワンポイントまで、とか。)
- 授業中の飲食禁止(飲み物くらい、いいやん。)
- 学力レベル関係なく全員同じ授業
- 毎回椅子を運び出しての、体育祭の予行練習
- 生徒が先生を評価するしくみがない。
- 何か理由を聞いても基本は「校則だから」の一点張り
もう遠い昔のことなので、その他たくさんの事を忘れてしまってる気がしますが、私は基本学校が嫌いでした。「みんな同じようにしなきゃダメ」というのがとにかく嫌い。
勉強する理由は親からも先生からも「受験のため」「あなたの将来のため(ざっくり)」と言われていたので、厳しい母親に家に入れてもらえないor怒鳴られる点数(79点以下)を取らないことだけを目標に、数学まで暗記する始末。(問題を暗記すれば、大抵は数字を入れ替えて正解を出せる。)
家庭が揉めていてしばらくの間すさんでいた私は、はしゃぐ同級生を冷めた目で見て(時に、仲間外れにされない程度にテンションを合わせて)、ある程度の学力と深入りしない人間関係を築くコツを手に入れながら大人になりました。
しかし、思春期である10代に家庭環境や友人関係、自分の将来や何のために生きているのかについて悩み考えるのは、きっとごく普通のこと。この頃のイジメ経験や各方面へのイラつきが当時の私の人格に影響していたのは否定できませんが、それが生き辛さと直結しているかと問われれば、答えはNOです。
ただ、直結はしていなくとも、ベースとしての私が無関係な訳ではないので、ある意味の自己紹介として書き出してみました。本当は感情豊か(良くも悪くも)なのに、周囲から一定の距離を置いて自分を守る感じ、恐らくわかってくれる方もいるのではないでしょうか?
それでは、20代、30代になっても消えずに、むしろ重さが増してきた私の日本での生き辛さについて、書いてみたいと思います。長くなったので前編・後編と分けてお送りします。どうぞお付き合いくださいませ。

私は福岡で生まれ、前職のリクルートで熊本に異動するまでずっと市内で暮らしていました。その後2014年に東京へ引っ越しましたが、多くの人と同様にずっと日本にいたわけです。
ソフト面もハード面も、日本語が話せてその文化を肌で知っている日本人にとって、日本ほど暮らしやすい国はないと今でも思っています。これまで15ヶ国ほど旅行で訪れましたが、そのたび頭の中でいつも思います。「日本って、便利だな」と。
- コスパが良くバリエーション豊かな食事面
- 丁寧な案内のある電車、きれいな道路などの交通面
- 綺麗なトイレなどの公衆衛生
- 先進的な建物、手入れされた緑など都市としての美しさ
- 話題のイベント、流行に敏感なオシャレな人々
- 口にせずとも相手の意図を汲み取ろうとする優しさ
- 夜の外出を怖がらずに出来る安全面
きっとまだまだあります。海外に少しでも出てみるとわかる、日本の心地良さ。特に日本で生まれ育った人にとって、この国で暮らすメリットはたくさん溢れているはず。(勿論社会問題や多くの課題もありますが、今はそこには触れません。)
頭ではわかっているし、「日本の良いところは?」と聞かれたらこんな風に色々挙げられる。それなのに時節、心をよぎる「このまま一生過ごしていくの?」という想い。そう、「頭」じゃなくて「心」をよぎる感じがずっと続いていました。
なんで皆同じような価値観なの?
なんで大多数に合わせるの?
なんでこんなに甘っちょろいの?
なんで私は周りの目を気にしているの?
前編はここまで。
後編で、「なぜ生き辛いと感じるのか?」私なりに考えて出てきた答えを言葉にしてみます。
【おまけ】
2012年に15年ぶりの海外旅行、アメリカに行ったときに読んだANAの機内誌。なぜか心に響いて、携帯で写メを撮っていました。日常生活の中でもたまに見ていたので、どこかで私の潜在意識に影響を与えていたのかもしれません。
以下、ANAの60周年広告。
(※著作権の関係で、実際の広告は載せていません。)
何もしなければ何も起きない。
行かなければそれはやってこない。
飛びださなければ世界は変わらない。
すべてのひとの心に翼はある。
使うか、使わないか。
世界は待っている。
飛ぶか、飛ばないか。
海をこえよう。
言葉をこえよう。
昨日をこえよう。
空を飛ぼう。
雲に向けて飛んでいく飛行機の写真もなんだか素敵なので、気になる方はコチラをどうぞ。 実際の広告が見られます。(リンク先はANAの公式Facebookです。)
(かっしーの感想)
私の学生時代は部活とプリクラの角度ぐらいしか考えていなかったような気もしますが、物事を問う人は色々な疑問を考えているようですね。
特に自分とは価値観の違う質問を部下にされる場合においては、人は結構「ルールだから」という免罪符で人をマネジメントしようとしますが、人は納得がいかないと従わない合理的な側面を持っています。だからこそ、いつも問いたいですよね。なんでそう思った?というのを。自分自身に。
北原 和司子 (きたはら わかこ)
(株)JALカーゴサービス、(株)リクルートジョブズを経てウイッグ事業で起業。その後メーカーでの新卒採用業務やスナックでの接客、住宅情報誌&ネットのADなど幅広い業界を経験し、フリーランス営業へ。現在は海外移住を目指しメキシコシティにて奮闘中。
★他、執筆中の記事はこちらから→https://note.com/maenimaeni