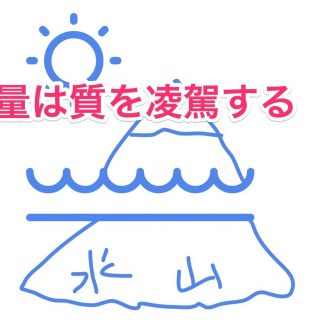柏木です。私は今日憤っております。
今日はりっきーがお客様先のセミナーに呼ばれてスピーカーでお話をするという、
とっても素敵でとっても貴重なありがたい機会だというのに、彼女がこちらが納得をいく練習をしないことに憤っております。何かしら人前に立って話をする以上、練習不足は一番美しくなく、ましてキャリアに関するセミナーというのは(私自身が失敗してきたからこそ最も痛感しているのですが)喋ってる自分に酔ってしまって、結果相手に伝えたいことが届かない。というケースが発生してしまう危険がモリモリなのです。
しかも今回は、会社設立して鹿児島で初めて社名とともにメンバーがお話しする瞬間です。
本当はそれを授業参観を見に行ったお母さんのように後ろからカメラ持参でワクワクそわそわ見たいにも関わらず、それが叶わないというちょっと悔しいシチュエーションにも関わらず、です。
そんな憤りを源に、本日は思いの丈をぶつけて参ります。
私たちはいつからプロになるのか。
私はプロのキャリアカウンセラーですが、同じ資格・同じ経験を持ったとしてもプロじゃない人がいます。その違いを、「自らがプロと名乗るか」という覚悟を定義にしました。
プロになった瞬間から、そこにはお金や実績や信頼など重たい責任がのしかかります。
出世したから管理職になった、入社式があったから社会人になったという分かりやすい始まりの日というものはなく、自分が覚悟し、名乗り始めた日こそがプロになる日だと思っています。
プロに求められるものは何か?
プロに求められるものは、専門的意見や知見だったりしますが、別枠に「この人になら任せても大丈夫」という安心感が求められています。それはプロ1日目だとしても10年目だとしても、安心感という同じ期待は込められているのです。
でも、1日目から10年目と同じ安心感を提供できることは稀です。その違い何でしょうか?
場数です。経験値です。
うまく行った経験も、胃の裏側に冷や汗をかく修羅場の経験も、全ての経験を持ってプロとして成長していくものだと思っています。だからこそ、場数が少ない時こそ、とにかく練習をするしかありません。
プレゼンテーターの手法にはいろんなスタイルがありますが、20代に分かりやすい言葉で話す、感受性の高い世代の注意をずっとこちらに向けるためにノイズをカットする。彼らを巻き込む。そういう必死な部分を含めて、当日の自分に期待を込めすぎるのは過信です。
スライドの内容は、PPTのメモにポイントを入れているのか?カンペは作っているのか?という細部まで準備をして初めて人に伝えたいことが残ると思っています。
そこまでして初めて表に立つのがプロだと、呼ばれる期待に応えられる時間を提供できるのだと私は戒めています。
で、こういう話をしながらいつも思い出すエピソードがあります。
「質が得意か、量が得意かは自分で決めろ。ただし、量は質を凌駕する」
超ぴよぴよだったリクルート1年目の頃、非効率に仕事をする私と対照的に、効率的に仕事をしてさっと帰っていく先輩がとても憧れで&悔しかったことがあります。
当時、ゼクシィのマネージャーと飲む機会があったので相談してみました。
私もあの人みたいになりたい。悔しい。と相談した時のアドバイスが今も思い出です。
「あなたの気持ちは分かる。量が得意・数より質で勝るのが得意な人、それぞれの強みだ。自分がこれから先どちらを得意としたいかを決めるのも、あなた自身だ。
もう十分、ビジネスモデルを体感する期間を経たはずだ。だから決めたらいい。自分は量をこなして仕事の質を上げていきたいのか、質を高めて確率高く仕事をしていきたいのか。
ただし、量は質を凌駕する。」
新しいことを始める時、慣れないことをする時、あの時マネージャーに相談したシーンが思い浮かびます。
氷山の一角を見せるためには、氷山が必要。
試行錯誤の日々は、こんなに準備運動ができないのかと思うほど、日々実践とトライアンドエラーの毎日ですし、それを自ら自走してやっているりっきーにとても感謝をしているのですが、私たちはプロとなったのでプロならではの準備と努力をしてほしいと思います。
準備なき勝負は単なる無茶な戦いです。試行錯誤のない場数は惰性です。
どちらも美しくありません。
準備してきた全てが出せなくて良いんです。準備した中から提供できるものがあれば。
努力の結果は、氷山の一角と同じぐらい「ちょい見え」で良いんです。
でも、氷山を作る努力や練習は必須で必要だと、私は思っています。
お気づきですか!
ほーら、思いの丈をぶつけるだけだとオチが見つからないじゃないですか!!
もうどうしよう!この話の締め方わかんないんだけど!!
株式会社ミライヘ代表取締役
GCDF-Japanキャリアカウンセラー/国家資格キャリアコンサルタント
転職や仕事の岐路を切り抜けるキャリア面談をやってます。
好きな食べ物:チキンカツ・ピザ あと、別軸で東京で1番小さい社長を目指してます。