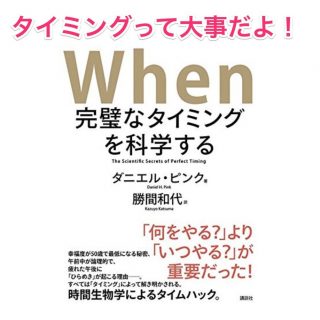柏木です。1つの題材で2つの記事が書けるのはこりゃあいいやと思っていたのですが、その間に伝えたいトピックスができてしまいました。こういうこともあるんですねぇ。
と言いつつ、Whenの続きです。
人には時間に関するタイプがあり、そのタイプによって集中できる時間の波やばらつきがあるよ、という共有が1回目。では2回目は、何かを始めるタイミングや、それを振り返るタイミングの力って大事なのよって共有です。
中間地点って大事。そして「始まり」は超絶大事。
「物事をうまく進めていくために大事なのは、HowやWhatより、Whenだわ」がテーマの本なので、始まり・中間・終わり。の大切さが書いてあります。
1日の中間地点や、プロジェクト、期間の中盤には人は中だるみをしやすい傾向が強く、その中だるみのまま進んでしまうと掲げていた目標に届かずに終わってしまう。という悲しい結果があります。
では、それをどうすれば良いかというと、「おっとこんな時間だ」と思わせるような気づきの時間が必要だと言われています。
1日の気づきなら、お昼や夕方のチャイムだったり、プロジェクトの気づきなら月の振り返りをするなどです。
なんとなくで流れて言ってしまう時間をあえて区切ることで、最後に辻褄を合わせる力が働き、より良い結果になりやすいというものです。
そして、その「おっとこんな時間だ」と思わせるために、始まりの「がんばるぞぉ〜」がとても大事になって来ます。
12/31に、その年の手帳を見て、「あぁぁぁあ今年の目標という恥ずかしいページを見つけてしまった」という絶望を感じたことある人いるかもしれないですが、
1/1に「今年はこんなことしたい!」と思わないと、絶望も途中の気づきもなくなってしまいます。今年の目標を立てたら、同時に自分の進捗を振り返るタイミングを決めると良いんです。その振り返るポイントはだいたい86個あると言われていて年度の始まりや自分の誕生日、会社の期の始まりなど何でも良いので途中で気づけるタイミングを設定するのが大事みたいです。
始まりも終わりも自ら作れるもの
ということで、HowやWhatだけでなく、When(いつやるのか)が大きく左右するということ。私たちが薄々知りつつ軽く見てた「時間」や「タイミング」がどれだけ大事なものになりつつあるのか?ということを知ることのできる本でした。
「世の中がグローバルになるということ、それは時差がなくなるということ。日本の日中や休日が海外の夜間や平日になる中で仕事をしていく機会が増え、ありとあらゆる仕切りの定義が薄れていく。前提そのものから見つめ直す世の中が、今、始まっている。」と、とある方から聞いたことがあります。
働き方が多様になることで、日々いろんな選択肢を手に入れる機会があり、手に入れると同時に「いつ何をやるのか」の決断に迫られています。
タイミングの大切さを見直すためにも、この本はおすすめです。
株式会社ミライヘ代表取締役
GCDF-Japanキャリアカウンセラー/国家資格キャリアコンサルタント
転職や仕事の岐路を切り抜けるキャリア面談をやってます。
好きな食べ物:チキンカツ・ピザ あと、別軸で東京で1番小さい社長を目指してます。